インタビュー INTERVIEW
インタビュー
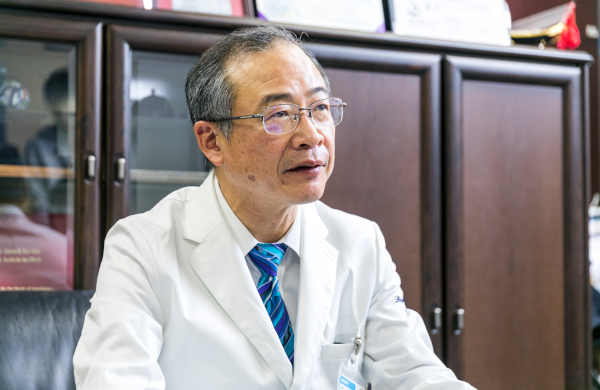
泌尿器科 顧問医
小川 修(おがわ おさむ) 先生
PROFILE
- 所属・職名
- 京都大学 医学研究科泌尿器科学 教授(インタビュー当時)
- ※現在:大津赤十字病院 院長
- 専門分野
- 泌尿器科腫瘍学
- 略歴
- 1982年
京都大学医学部卒業 - 1983年
田附興風会北野病院 泌尿器科医員 - 1991年
ニュージーランドオタゴ大学 研究員 - 1993年
京都大学大学院博士課程終了 - 1993年
京都大学医学部付属病院 泌尿器科助手 - 1996年
秋田大学医学部泌尿器科学講座 助教授 - 1998年
京都大学医学部泌尿器科学 教授 - 2021年
大津赤十字病院 院長
小川先生は、なぜ医師を志されたのですか。
幼少期は島根県・浜田市という田舎町で過ごしました。両親が教員をしていたこともあり「教員になるのが当たり前」と思い込んでいました。
しかし、広島の高校に進学し視野が広がると、もっと色々な可能性があることに気付いたのです。
理系が得意だったので、大学での勉強を将来の仕事に活かせる職業をと考えたときに、候補にあったのが医師でした。
泌尿器科を選ばれた理由もお聞かせください。
外科系診療科を志望していましたが、大きな診療科に行くことに抵抗がありました。なぜかというと、当時の京大病院は研修医であふれていたからです。外科は60~80名、整形外科でも30名以上...、それだと教授に名前も憶えてもらえませんし、なかなかチャンスも回ってきませんよね。そこで、マイナーなイメージがあった泌尿器科を選びました。
実は、医学部時代にはラグビー部に所属していて、そこで泌尿器科の恩師にあたる吉田修教授が顧問をされていたことも影響がありましたね。
泌尿器科の醍醐味は、なんといっても外科的なこと、内科的なことを含めて、全身にアプローチができるということです。
循環器なら循環器内科と腫瘍血管外科、消化器なら消化器内科と消化器外科...というように、どの診療科もカウンターパートがいるのですが、泌尿器科のカウンターパートは腎臓内科ではなく"泌尿器科自身"なんです。
先生は40歳の若さで教授にご就任されています。それまで、どのようなご苦労があったのでしょうか。
私自身が好んで選んだ訳では無いのですが、何もないところからモノを創り上げる経験を何度もさせていただきました。
吉田教授から言い渡された大学院の研究先は、分子生物学の実験室が無かったため、実験室作りから始めましたし、留学したニュージーランドでも、最先端というほどの研究体制に恵まれていたわけではありませんでした。
京大の助教をしていた1996年、秋田大学への赴任を言い渡されたのですが、泌尿器科がんの研究ができること、腎臓移植の経験があることの2点から、私が選ばれたと聞いています。縁もゆかりもない地で言葉の面でも戸惑いました。
私自身は大したことをしていないのですが、教室員達と腎臓移植を立ち上げ、がんの基礎研究ができるような実験室をセットアップしました。
吉田教授が1年早く退職され、秋田着任2年後の1998年に思いもかけず京大泌尿器科の第6代の教授に就任しました。
小川先生が医師として最も大切にしていることをお聞かせください。
臨床実習で泌尿器科に回ってくる学生と、一週間に一度お昼ご飯を一緒に食べるのですが、そのとき「一流の医師ってどんな医師だと思う?」って必ず聞いています。「芸能人格付けチェック」というお正月番組がありますよね。歌手や芸人、俳優が出てきて、ワインや盆栽の本物を見極め、一流の芸能人か三流の芸能人なのかを判別するバラエティ番組です。一流の芸能人とは歌が上手いだけではないし、良い演技ができるだけではない。色々な芸術、文化が理解できて、初めて一流の芸能人だというコンセプトの番組です。言い換えれば、いろいろな芸術や文化に造詣が深くないと一流の芸事はできませんよという事です。
翻って一流の医師とは何かです。「手術ができる人」「 薬の知識に長けている人」、もちろんそれは医師に必要な素養ですが、それだけではありません。
例えば、自分で臨床研究を立ち上げたことがあるとか、基礎研究に少しでも携わったことがあるとか、そういったいろいろな経験を積み重ねることによって、初めて「一流の医師」になれると思っています。できたら医学以外の色々な分野にも造詣が深いことに越したことはないと思います。私自身はラグビーをやっていましたし、ゴルフも大切な趣味です。これを通じて学んだチームワークや忍耐力などは今に生きていますし、他分野の友達とのつながりにも役だっています。
ですから、若い医師たちには医療だけでなく、さまざまな分野にアンテナを張っていただきたいですね。それが、今後の肥やしになってくるはずですから。
がんの部位別罹患数において、前立腺がんは男性の2位であり、また、増加傾向が著しいがんのひとつとされています。なぜ増えたのでしょうか。
ひとつは環境要因です。前立腺がんは、欧米諸外国の男性患者数が最も多いがんであり、日本でも生活様式・食習慣の欧米化により、罹患率も死亡率も増加傾向にあります。もうひとつは高齢化によるもの。さらに申し上げると、血液腫瘍マーカー(PSA)による検出の向上により、早期発見率が飛躍的に高くなったことが大きく関わっています。
PSAとはどのような検査なのでしょうか。
前立腺から出される酵素で、通常は精液中に分泌されるのですが、がんになるとPSAは血液中に漏れ出します。それを血液検査で検出することでがん疑いの方をピックアップできます。PSA値が4~10ng/mLはいわゆるグレーゾーンでがんである可能性は10~20%、10 ng/mLを超えてくると50%の割合でがんが発見されます。ただし数値が基準値を超えたからといっても、必ずしも前立腺がんとは限りません。
基本的には50歳以上の方が検査の対象になります。ただし、父親と兄弟に前立腺がん歴がある場合、リスクが2、3倍に増加することが報告されていますから、そのような方には40代後半から血液検査を受けられることをお勧めしています。
そしてがんの疑いがある場合には、診断のために前立腺生検を行います。最近ではMRIとエコーの画像を融合してターゲットをはっきりさせ、そこに針を刺して組織を採取するMRI Fusion生検を採用しています。先進医療になるので10万円ほどの費用負担が必要になりますが、近年はこの生検の精度向上で、これまで発見できなかったがんも見つけられるようになりました。
前立腺がんは生存率が高いというデータもあります。また進行が遅く、なかには寿命に影響しないがんもあるとも聞きますが、やはり検診は受けた方がいいのでしょうか。
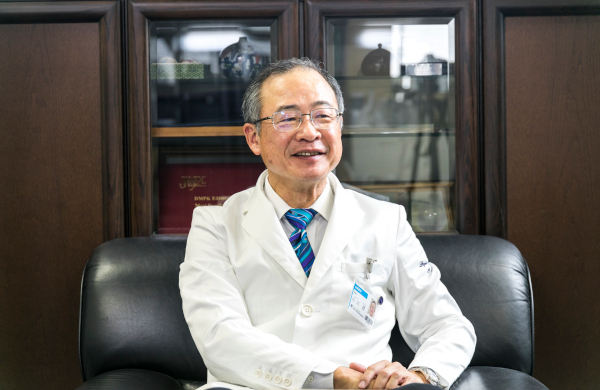
前立腺がんは、初期に発見された場合には10年生存率が100%というデータがあるほど、生存率が高く予後のよいがんです。
しかしながら、放置するとそのまま進行して、治療が難しくなる危険も潜んでいます。早期に適切な治療を受けるためにも、あるいは未来のリスクを回避するためにも、私は検診を勧めています。
ただ、中には、がんの発見が直ちに治療の必要性とつながらない患者さんもありますので、検診の意義を充分理解してうける必要もあります。
前立腺がんの場合、どのような治療を行うことになるのでしょうか。
がん治療は「手術」「放射線療法」「薬物療法」が三大療法と呼ばれ、前立腺がんの場合もこれらを選択することがほとんどです。
がんが前立腺にとどまっている場合は手術や放射線療法での治療が有効ですが、転移している場合は、進行を抑えるための薬物療法が中心となります。
京大では年間200名以上の前立腺がん患者さんを診ていますが、だいたい20%の患者さんが薬物療法、40%が放射線療法、40%が手術で治療を行っています。手術はすべて「ダ・ヴィンチ」という手術支援ロボットを使用した内視鏡下手術を行っています。
「ダ・ヴィンチ」のご利用状況はいかがでしょうか。
京大では初号機を2011年に導入しました。前立腺がんのロボット支援手術をアメリカで目の当たりにして「すごい」と思ったのが2001年のことでしたから、10年のタイムラグがあったわけです。手術ロボットの導入以前から日本は内視鏡手術の世界的トップランナーで、内視鏡手術の技術力は高いレベルにありましたので、手術ロボットが認可されてからは、ものすごいスピードで全国に広がりました。現在は全国で300台を超えるロボットが稼働し、さまざまな診療科の手術に適応が拡大されています。
ロボット支援手術の泌尿器分野での保険適用においては、2012年の前立腺がんを皮切りに、腎がん、膀胱がんと順次広がってきました。手術数は一時、前立腺がんに集中していましたが、保険適用に伴い、最近では腎臓がんや膀胱がんの手術が増えています。
なお、京大では最新機種「ダ・ヴィンチXi」を導入しています。それまでの機種に比べて、セッティングまでの時間を短縮できるのが一番の違いです。基本的に動きも手術方法も前機種と変わりはないのですが、車でたとえるならカローラとレクサスくらい扱いやすさが異なります。
ロボットで手術を行うメリットについてお聞かせください。
医療従事者にとっては明確にメリットがあります。これまでは4、5時間、長ければ8時間越えの手術を立った状態で、なおかつ窮屈な姿勢で行っていましたから、座って、落ち着いて手術できるのは体力的にも非常に助かっています。また、3Dカメラで立体的に映し出し、患部を拡大視野でとらえることができる点も、これまで以上の正確な手術につながっています。
患者さんにとっては「ロボット支援手術の方が絶対に優れている」と言える段階にはありません。「根治率が上がる」「合併症が減る」「医療費が安くなる」の3つが、ロボット支援手術の良し悪しを決める指標になると考えられます。
ひとつ目の「根治率」は結論が出ていません。なぜなら、開腹手術と同じ条件で比較しなければならないのと、結論が出るまでには10年以上の患者さんの経過観察が必要だからです。二つ目の「合併症」に関しては、術中の出血、性機能障害や排尿障害などのリスクを大幅に回避することができるという意味でロボットの方が明らかに優れています。三つ目の「コスト」ですが、ロボット手術は高額になります。
昨年は本庶先生のノーベル賞受賞が大きなニュースとなりましたが、泌尿器治療における免疫チェックポイント阻害薬の活用状況はいかがでしょうか。
泌尿器科で扱うがんのうち、治験をクリアして安全性や有効性が認められているのは、腎臓がんと尿路がんの2つです。
なかでも腎臓がんは、最初に免疫チェックポイント阻害薬が認可されたがんです。腎臓がんの治療の歴史は紆余曲折で、私が研修医だった頃は、どのような薬物療法も効果はそれほど期待できず「外科的に取る」しかありませんでした。それが、10年前からは分子標適治療薬が用いられるようになり、治療成績がぐっと高まりました。そこに免疫チェックポイント阻害薬が新たに加わったのです。
ただ、いま腎臓がんで使える薬は10種類程度あるのですが、それをどういう順番で使うのかわかっていないのは大きな課題です。
進行性の膀胱がんに関しては、これまで、20年以上に渡ってシスプラチンという抗がん剤治療しか選択肢がなかったのですが、免疫チェックポイント阻害剤の登場で、治癒につながる治療が可能になりました。効く人にはすごく効きますが、恩恵を受ける患者さんは10人に1人か2人の割合です。誰に効くのか今はわかりません。課題が山積みですね。患者さんは毎日来院されますから、自分たちの経験や世界から発信される論文の知識を総動員して、チャレンジするしかありません。
これらの課題解決には、マーカーが必要です。このマーカーなら免疫チェックポイント阻害薬、このマーカーなら分子標的治療薬という答えが見つかれば、より効果的な治療が受けられるようになると考えます。世界中の研究者が精力的に研究を進めていますが、見つかるまでにこの先10年はかかるかもしれません。
がんの発生要因の一つには家族歴もあるようです。泌尿器がんに関して、遺伝子が及ぼす影響や、遺伝子検査の将来性についてお聞かせください。
遺伝子検査のメリットのひとつは、がんの原因となる遺伝子の異常が分かり、その結果によって、より効果があると考えられる薬の開発や選択ができることです。腎臓がんでは生まれつき腎臓がんになりやすい家系があります。この家系の遺伝子解析から原因遺伝子(VHL遺伝子)が明らかにされ、その機能を解析することにより、分子標的治療薬の開発につながりました。また、膀胱がんに関しても原因となる遺伝子が特定され、遺伝子分類をもとに治療戦略を立てるというところまできています。今年の6月に遺伝子検査が保険適用になりますから、より個別化医療が前進することになるでしょうね。
関西メディカルネットの会員の方々へメッセージをお願いします。
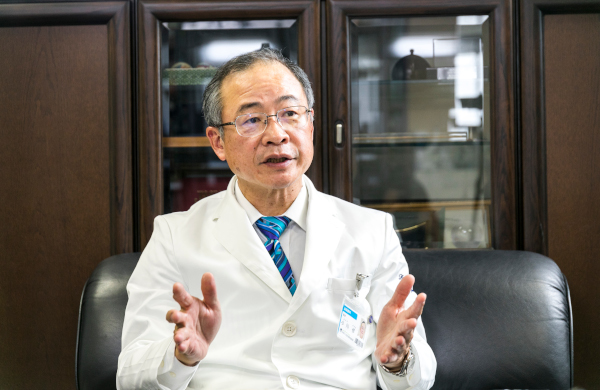
早期発見・早期治療は非常に重要なことです。進行すればするほど回復時間も、お金もかかりますし、体力的な面でもご負担になることでしょう。できれば検診をもとに正しい知識を得て、食生活の改善や運動など、いわゆる予防にまで気を配っていただけたらと思います。
※2019年2月20日取材
BACK