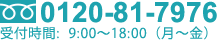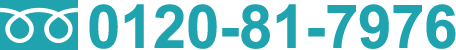2016.05.13
体調管理
深刻な疾患を引き起こす前に......早めに取り組みたい、高血圧の予防策
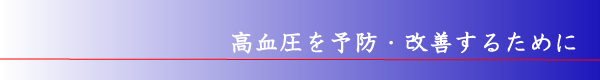 5月17日は「高血圧の日」。これは5月17日の世界血圧デーに合わせ、日本高血圧学会と日本高血圧協会が、高血圧予防を広めるために制定したものです。
5月17日は「高血圧の日」。これは5月17日の世界血圧デーに合わせ、日本高血圧学会と日本高血圧協会が、高血圧予防を広めるために制定したものです。
高血圧とは、血圧の高い状態が続く病気です。血圧が高くてもすぐに症状が現われるわけではありませんが、その状態を放っておくと、血管が傷めつけられ、動脈硬化が進んでしまいます。動脈硬化が進行すると、血管が破裂したり詰まってしまうため、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、くも膜下出血など、命を脅かす病気の発症リスクを高めてしまいます。
そんな恐ろしい事態に至らないためにも、高血圧は早めに予防することが大切です。今回はそんな高血圧の予防ポイントについてご紹介します。
◆塩分を控える
塩分を多く摂っている人ほど血圧が高い傾向があるようです。それは塩分を摂りすぎると、塩分濃度を薄めようと身体が血液中の水分量を増やそうとするためで、その結果、血管が膨らみ血圧が上昇してしまうのです。1日の食塩摂取量は、高血圧の人の場合、6g未満が望ましいとされています。予防のためにも、厚生労働省などが推奨する「塩分を控えるための12ヵ条」を参考に、減塩に取り組んでみませんか。
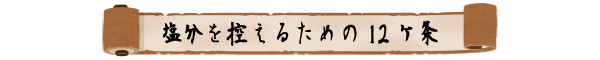 ① 薄味に慣れる……
① 薄味に慣れる……
昆布やカツオブシなどで出汁をとると薄味でも風味豊かになります。
② 漬け物・汁物の量に気をつける……
漬け物や汁物は塩分が豊富。食べる回数と量を減らしましょう。
(ラーメンなどを食べるときはスープを残すようにします)
③ 塩は効果的に使う……
塩は食べ物の表面にサッと振りかけると少量でも塩分を感じることができます。
④ 「かけて食べる」より「つけて食べる」……
塩分の多いしょう油やソースは器に入れ、必要に応じてつけて食べましょう。
⑤ 酸味を上手に使う……
和え物や焼魚にはレモンなど柑橘類や酢をかけると味に変化がつけられます。
⑥ 香辛料をふんだんに使う……
唐辛子やコショウ、カレー粉など香辛料も、減塩調理に効果的です。
⑦ 香りを利用する……
香りのある野菜(ゆずやしそ、ハーブなど)、海苔、カツオブシなどを加えると、
味付けに変化がつきます。
⑧ 香ばしさを味方に……
炒りゴマやクルミの香ばしさが塩分の摂り過ぎを抑えます。
⑨ 油の味を利用する……
ゴマ油やオリーブオイルの風味も塩分抑制に活用できます。
⑩ 酒の肴にご注意を……
酒肴には塩分が多いので量は控えめに。
⑪ 練り製品・加工食品にも気をつけて……
カマボコなど魚の練り製品、ハムなど肉の加工食品も塩分を多く含みます。
⑫ 食べ過ぎに注意……
せっかくの減塩料理も、食べ過ぎては台無しになります。
◆野菜・果物を積極的に食べる 野菜や果物にはビタミンや、カルシウム、カリウム、マグネシウムといったミネラルが豊富。これら栄養成分は高血圧の予防・改善に役立つといわれており、このうちカリウムには塩分を体外に排出する働きがあります。カリウムはジャガイモなどの芋類や、ニンジンなどの根菜類により多く含まれています。そんな野菜類は、一日に350g以上は摂りたいもの。毎食1皿以上食べるよう心がけましょう。野菜は生のままより加熱したほうが、かさが小さくなるので無理なくたくさん食べられます。果物では、カリウムを多く含むバナナやリンゴ、キウィなどがお勧めです。ただしバナナは糖分も多いので、食べ過ぎには注意。1日1本を目安に食べるといいでしょう。
野菜や果物にはビタミンや、カルシウム、カリウム、マグネシウムといったミネラルが豊富。これら栄養成分は高血圧の予防・改善に役立つといわれており、このうちカリウムには塩分を体外に排出する働きがあります。カリウムはジャガイモなどの芋類や、ニンジンなどの根菜類により多く含まれています。そんな野菜類は、一日に350g以上は摂りたいもの。毎食1皿以上食べるよう心がけましょう。野菜は生のままより加熱したほうが、かさが小さくなるので無理なくたくさん食べられます。果物では、カリウムを多く含むバナナやリンゴ、キウィなどがお勧めです。ただしバナナは糖分も多いので、食べ過ぎには注意。1日1本を目安に食べるといいでしょう。
◆体重をコントロールする
肥満の人は平均体重の人と比べ、高血圧の発症率が2倍から3倍高くなるといわれています。食事は腹八分目を心がけ、週1回は体重計に乗って測定するなどし、つねに体重のコントロールに努めましょう。
◆飲酒はほどほどに
過度の飲酒も高血圧の原因です。高血圧予防としての許容飲酒量は、1日当たり日本酒1合程度。週1日以上は休肝日も設けましょう。
◆運動習慣を持つ 高血圧は運動でも予防できます。少し息が切れるくらいのやや強めの有酸素運動がお勧めです。運動習慣のない方は、1日30分以上のウォーキングから始めましょう。
高血圧は運動でも予防できます。少し息が切れるくらいのやや強めの有酸素運動がお勧めです。運動習慣のない方は、1日30分以上のウォーキングから始めましょう。
※上記を行う際、すでに高血圧を指摘されている場合は、いずれも医師などに相談してから始めてください。
高血圧は典型的な生活習慣病であるため、予防には日々の生活を見直すことが望まれます。ただ、長年の生活習慣を自分一人で変えることは、かなり大変なことかもしれません。そんなときは、関西メディカルネットがご提供するメディカルサポートシステムの「生活習慣改善プログラム」がお役に立ちます。パーソナルアドバイザーがきめ細かにサポートする本プログラムでは、その方に適した方法をご提案しているので、無理なく生活習慣の改善にチャレンジしていただけます。高血圧が気になる方も、ぜひ本プログラムをお試しになり、深刻な疾病に至るリスクを早めに回避してください。
■「生活習慣改善プログラム」についてはこちらまでお問い合わせください。 https://www.k-medicalnet.co.jp/mssmember/inquiry/